ケアマネからの事前情報
ケアマネジャーからの事前情報はこうだった。
「70代女性、精神疾患あり。要介護2独居。そして、ゴミ屋敷の可能性があります。」
珍しくはないけれど、やはり少し身構えてしまう内容だった。
「独居」と聞いていたが、実際に訪問してみると、玄関の向こうには明らかにもう一人の気配。
対応に出てきたのは息子さん。物腰は柔らかく、受け答えもごく普通だったが、家の中は予想を遥かに超える状態だった。
「母の体調が悪いので、しばらく一緒に住むことにしたんです」
そう話す彼の後ろに広がっていたのは、まさに“生活の限界”とも言える風景だった。「どうしていいかわからなくて…。」と息子さんも何から手を付けていいかお手上げ状態。
目の前に広がる“現実”
玄関を開けた瞬間、まず感じたのは、強い生活臭と空気の重たさ。
足の踏み場もないほどに積み上がったゴミ袋や雑誌、ペットボトル。
かろうじて人が一人通れる細い通路が、奥の部屋へと続いていた。
奥で寝ていた利用者さんは、体調が思わしくなく、動くこともままならない様子。
けれど、その周囲にも物が溢れかえり、介助を行うスペースすらない状態だった。
このままではヘルパーが安全に入ることも、基本的なケアを行うこともできない。
そこで責任者2人がかりで、まずは“住環境の整備”から始めることになった。
ゴミに埋もれた「暮らし」の再構築
床に積み重なる米袋の中身は、5年前に賞味期限が切れて変色した米。
冷蔵庫には10年以上前の合わせみそが10袋以上、赤みそのような色に変わっていた。
棚には砂糖や塩、みりん、料理酒が山ほど積み上がり、床板が抜けそうなほどだった。
息子さんに一つひとつ確認を取りながら、
「これは使えませんね」「これも捨てていいですか?」と声をかけ、
許可を得たものから丁寧にゴミ袋へ詰めていく。
“口に入れても問題なさそうなもの”を見極めながら、
ヘルパーが調理できる空間を、少しずつ整えていった。
こうしてようやく、清拭や更衣、調理といった本来のケアにたどりつくことができた。
心が動き出した瞬間
最初は、私たちが次々と物を捨てていく姿を、利用者さんは不安そうに見つめていた。
「それ、まだ使えるかも…」「捨てんといて」
そんな言葉が小さくこぼれる。
けれど、身の回りが少しずつ片付き、あたたかいタオルで体を拭き、
清潔な服に着替えると、徐々に表情が柔らかくなっていった。
キッチンからご飯の炊ける匂いや味噌汁の香りが漂う頃には、
ぽつりぽつりと会話もできるようになっていた。
「こんなふうに、人が来てくれるの、久しぶりやな」
「家って、こんな匂いやったんやね」
息子さんも次第に少しずつ会話に加わり、
「このへんは僕がやっておきます」「次までに片付けておきます」と自ら動くようになった。
訪問介護という仕事の誇り
本来、ここまでの片づけは訪問介護の業務範囲外なのかもしれません。
ケアマネジャーさんも「こんなこと頼んで申し訳ない」と頭を下げておられました。
でも、私はこのエピソードを忘れません。
「家で暮らしたい」
その当たり前の願いを叶えるために、私たちは奔走しました。
人にはそれぞれ、“自分の家”があります。
そこにはその人なりの価値があり、思い出があり、手放せない何かがあります。
訪問介護は、その超プライベートな空間に足を踏み入れ、
その人の生活を支え、時に立て直していく仕事です。
私はこの仕事に、心からの誇りを持っています。
次回の記事では、「介護職が実践する、家族とのコミュニケーション術」についてお話しします。
今回は、利用者さんの住環境を整えることで「家で暮らす」希望を支えましたが、時に介護の現場では家族とのコミュニケーションが非常に重要になります。
「介護ストレス」「家族の理解を得る方法」など、家族とどのように連携し、支え合っていくかについて、実際のケースを交えながらご紹介します。
介護現場でのリアルなやりとりに興味がある方は、ぜひ次回もお楽しみに!


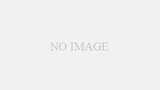
コメント